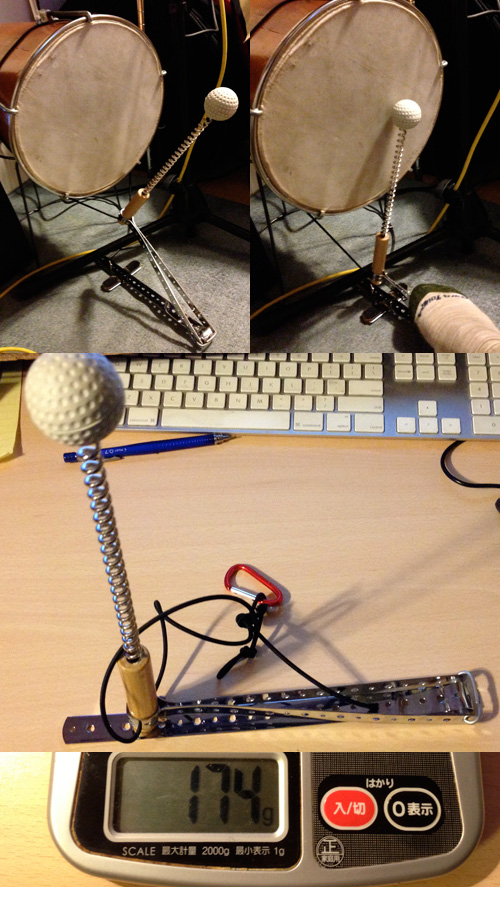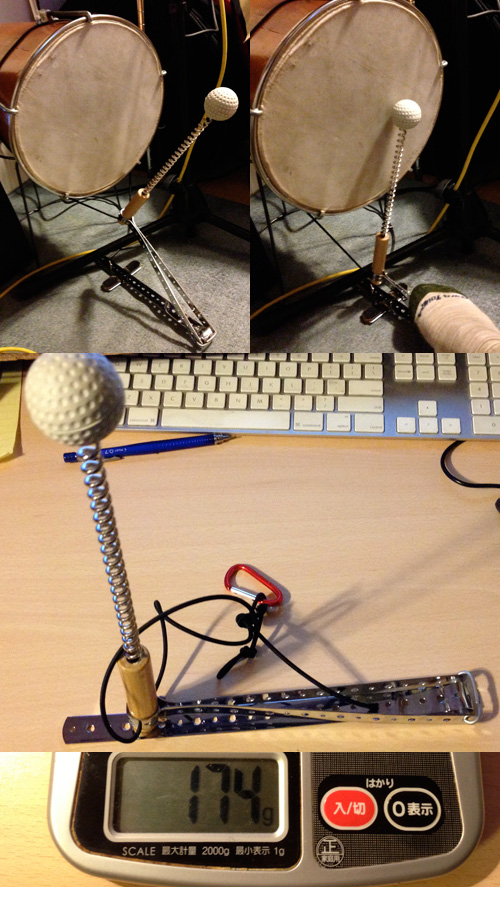2013年03月14日
シンバル・チューニング特集とシンディ・ブラックマン・サンタナ・ドラムクリニック
この日記に載せた「シンバル・チューニング」の内容を実際にスタジオで試した特集記事が、今月発売のドラムマガジン2013.04月号に掲載された。これ、嬉しいことですね。先人ドラマー達のアイデアや自分の実験も含めていろいろな人に知ってもらえるということでもあるし、ドラマー達がいろいろやってみることにつながると良いなぁと。おそらく「もっといろんなアイデアがあるぜ」「俺はこうするけどな」なんて人もいることだろうとも思うし、「なんでこんなことするんだろう」と思って、今一度自分の音を聴き直す人がいたら一番の成果なのだろうと思う。シンバルは、そのまま朗々と鳴らすのが一番ではあるけれど、ドラムという楽器の特性上、場所や楽曲、他の演奏者との絡みで気になることが出てくるのも致し方ないところ。最終的には楽器から音を引き出す技量の問題になるけれども、そのプロセスに実験があるということでいいのではないかと。
昨晩は、秋葉原のドラムステーション主催の「シンディ・ブラックマン・サンタナ」のドラムクリニックにお邪魔させていただいた。一応イベントレポートということでライターモードで行ったわけだけれども、なんともソウルフルかつアカデミックな内容だった。以前シンディがイスタンブールに移って自分のモデルを出した時に、なかなか作れそうで作れなさそうなシンバルの出来具合を見て、聡明かつディレクションの的確な人なのだろうと想像した。昨晩は自己紹介の後に演奏を披露、その後のQ&Aが実に真摯な回答の連続で、ついには1930年代からのアメリカのドラムの歴史を実演をおりまぜながら解説。バック・ビートスタイルの中にも、ジャズの要素を活かすことが重要であるということを説明していた。まるで自分の原稿か授業のようでもある。実際、あの場にいた若者達はどこまで理解したのだろうか、そして興味を持ちきることができるのだろうかと思うのだが、やはりドラマーとして重要なポイントを、彼女もまた先人ドラマー達から継承し、それをまた下の世代に伝えようとしていたのが素晴らしい。演奏も、過度なアタックを出さないナチュラルなトーンを中心にした音で、しかしそれが演奏になると個々の音がせめぎ合って紡ぎ合う中にエネルギーが生まれるものだった。これについては、仕事としての原稿が終わった後に、このセミナーの内容を細かく書きたいなと思う。
2013年03月17日
ジャスティン・フォークナー Justin Faulkner
2011年9月28日、コットンクラブでカート・ローゼンウィンケル・トリオを聴いてその実力にため息をつかずにはいられなかった若い天才ドラマー、ジャスティン・フォークナー。昨年にはStar of Jupiterというカートの新アルバムが登場、そのツアーで日本でも実現し、昨晩は赤坂草月ホールにて最終公演が行われた。
ドラマガ編集部のKTN氏に声をかけていただき、インタビューに行ってきた。サウンドチェックからスタンバイし、音出しから構成チェックまでの様子を眺めながら、2年前よりもさらに確実にさらに表現の幅が広がっているジャスティンのドラミングには、なにかこう、目の前で生きているものというよりは、完成された映像がホログラムで流れているのではと思うところもあり。
しばらくして、撮影とインタビュー開始。以前にも増して英語が聞き取れなくなっている自分と、インタビューの才能は無いなと改めて感じながらも、やはり自分が機会を与えられたからには、自分由来の質問をといくつかさせていただいた。それについては、ドラムマガジン誌上でお伝えできるように原稿調整など頑張りたくてたまらないというところ。
インタビュー後の本番は素晴らしかったとのこと。あいにく自分のレッスンに戻らねばならず、それは体験出来なかったが、あのサウンドチェックだけで十分に想像できる。ジャスティンに限らず、エリック・ハーランド、クリスデイヴ、ケンドリックスコット...若き天才が溢れる時代です。
ジャスティン・フォークナーと。